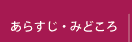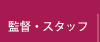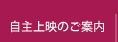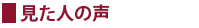
 ★ 全く知らなかった世界に近づくことができました。なんて純粋、なんてキラキラした目のビラル。人の生活って一体何なのだろう。盲目のお母さんお父さんのたくましさにも心打たれました。あっという間の90分でした。(高橋典子[料理研究家])
★ 全く知らなかった世界に近づくことができました。なんて純粋、なんてキラキラした目のビラル。人の生活って一体何なのだろう。盲目のお母さんお父さんのたくましさにも心打たれました。あっという間の90分でした。(高橋典子[料理研究家])★ 誰のせいでもない運命を受け入れ、笑いながら泣きながらケンカしながら生きているビラルの家族。そのあたりまえのことが、あらためて語りかけてくるような映画でした。インドの中でイスラムの人々が暮らす地域の生活もイキイキと描かれていました!(新井容子[フリーライター])
★ 最初観たとき、すごい!と思ったが、二度観たとき さらにすごい!と思った。何度でもひたりたい世界!(来栖真喜子[50代])
★ ビラルの世界は、汚くて、かなり騒々しくて、ごちゃごちゃしていて……、我々の世界と同じでした。あの瞳があれば何かできそうな気がしてきて、自分の目をわざとパチクリさせてみると、少し笑顔になります。(荒井博樹[新聞社勤務])
★ バイタリティーにびっくりしました。喧噪のなか、いろいろ苦難はあるのでしょうが、なんともみんなが人間くさくて、なぜか元気になりました。(齋藤敦子[インターナショナル・スクール勤務])
★ 「家族の絆」とはお互いの手触りでの確かめ合いとともに容赦のないお仕置きであり、「友情」とは年上が年下を体を張って守りながら時にはケンカ相手に手加減せず石をぶつけることだったり。その厳しくも美しいリアリティは、我々が貧困層を取材する際に慣用句として使う「貧しい生活の中にある本当の優しさと命の輝き」などといった安っぽいヒューマニズム表現をあざ笑う。直視し続けるのが苦しいほどの過酷な現実を「よく見ろ」と、奇跡のような輝く映像が挑発し続ける。何度も声を上げて大笑いしながら、涙止まらず。劇場を出た後もいつまでも心臓の高鳴りがおさまらなかった。(尾崎竜二[テレビディレクター])
★ 実に強烈で快活で、人間が本来持っている生命力を 五感でまるごと感じる映画でした。(望月政秀[広告代理店アカウントディレクター])
★ オーディトリウム渋谷で映画「ビラルの世界」を観てきました。盲目の両親とともにインドのコルカタ(カルカッタ)で暮らす、3歳の少年ビラルの日常を追ったドキュメンタリーです。といっても、涙なくして見られない、とか、なにか教訓的な、とか、そういうふうでなく、大家族の暮らす狭い部屋、雨水のあふれた路地裏、路地の入り組んだスラム街、走り回るネズミ、空の月、といった映像と、子供たちの喧嘩や大人の怒鳴り声、街の喧騒と言った音声のおかげで、インドに、というか文字通り、「ビラルの世界」に、どっぷりと浸った80分でした。宗教の違いを乗り越えて結婚した盲目の両親は、詐欺に会って借金を抱え込んでいるし、一家は貧困の中にいることはたしかだけれども、可哀想、気の毒というよりも、私たちの日常とはかけ離れたようにみえる暮らしにも、人間の生きるところに必ず存在する普遍的な生活があることに気付かされます。ビラルは毎日小さな弟をたたいてはお父さんに怒られるし、お母さんは姑の口煩さに、婚家での生活にうんざりしています。お祭りになれば皆大喜び、新しい服を身につけるのは晴れがましい・・・。人によって、全然違った見方になると思いますが、私にとってはそういう映画でした。上映後、JICAインド事務所に勤務していた方のトークがありました。そこでも、話題に上りましたが、教育で生活は変わります。3歳ですが、ビラルは学校に通い、英語の勉強をしています。インドは、数学教育に秀でたIT大国の側面もあります。10年後、インドは、ビラルはどのようになっているでしょうか。そして、日本は?(岡野淑乃 [慶應大学非常勤講師])
★ 『ビラルの世界』を通して人間という生き物に備わったたくましさを再発見できた気がします。(森岡清人[航空会社勤務])
★ 映画を見て、「怒る」「喧嘩する」など、なるべく避けたい事を含め「人間の豊かさ」であるのだと感じました。なるだけ波風立たないように人間関係をうまく「こなす術」を身に着ける事が社会人、という雰囲気に抵抗を感じていただけに、ビラルの周辺でどんちゃん騒いでる人達を見て、爽快な気分に成りました。感情を表に露わにする事で、ぶつかっていく。その結果として、凹むときは凹み、喜ぶときは喜ぶ。感情が揺れることを恐れないでぶつかっていく事が、表情の豊かさにもなるのかなと思いました。皆が皆どこかで様子をうかがっている、その結果動けないでいる、どこか息苦しい、そんな風潮を感じつつ埋もれてしまう私ですが、どっこいしょと立ち上がってみます。(尾野慎太郎[24歳])
★ インドを舞台にした他の映画、例えば「スラムドッグ・ミリオネア」やブッカー賞受賞小説「グローバリズム出ずる処の殺人者より」(いずれも楽しんだけれど)からは感じることができなかった熱気、湿気、人いきれ、カレーその他もろもろ混じりの悪臭、五感で感じました。初めのうちはむせかえるけれど、プリミティブで感情剥き出しだけど人間クサーイ人たちの世界に入り、勿論そこには貧困という苦しくて痛々しい事情は有るけれど、先進国でそれなりに生きるため今日私達が封じ込めているものの存在を見せつけられた気がします。(吉森利映[50代主婦])
 ★ 電灯の無い、薄暗い穴蔵のような世界に始まり、目まぐるしく変わるシーンや視点、わざとずらしたような音の入り方は、私たち映画を見る者が、その世界に入り込めずに躊躇しているのと同様に、映画のほうからもこちらに対して一線を引かれているような感覚があった。やがて電灯が灯り、目が慣れてくるのに従って環境音と絵(映画のシーン)が馴染んでくるような感覚。ふと気が付くと、別世界のように感じていた空間の中に、いつのまにか引き込まれていたような感じがした。子供が育つ場所としては、最低限の衛生・安全面の環境が整っていない状態で、いつ誰が怪我をしても、病気になってもおかしくない状態なのに、笑顔とエネルギーが溢れていて、悲惨な雰囲気に支配されていない。むしろ、夫婦や親子が遠慮なくぶつかり合い、肌を触れ合い、感情を露わにする、こちらの生活のほうが、家族本来の自然なかたちなのではないかとさえ思えてくる。夫婦に子供がいて、生きるためにもがいている。人間として動物として、生き物としての基本がいっぱい詰まった生活。夫婦が互いに相手に対して抱く不満や期待も、とても身近に感じる内容だった。生きることの意味をはじめ、色々なことを考えてしまったけれど、結局のところ、『家族っていいな!』と気付くための映画なのかな、と思った。(彦根 明[建築家])
★ 電灯の無い、薄暗い穴蔵のような世界に始まり、目まぐるしく変わるシーンや視点、わざとずらしたような音の入り方は、私たち映画を見る者が、その世界に入り込めずに躊躇しているのと同様に、映画のほうからもこちらに対して一線を引かれているような感覚があった。やがて電灯が灯り、目が慣れてくるのに従って環境音と絵(映画のシーン)が馴染んでくるような感覚。ふと気が付くと、別世界のように感じていた空間の中に、いつのまにか引き込まれていたような感じがした。子供が育つ場所としては、最低限の衛生・安全面の環境が整っていない状態で、いつ誰が怪我をしても、病気になってもおかしくない状態なのに、笑顔とエネルギーが溢れていて、悲惨な雰囲気に支配されていない。むしろ、夫婦や親子が遠慮なくぶつかり合い、肌を触れ合い、感情を露わにする、こちらの生活のほうが、家族本来の自然なかたちなのではないかとさえ思えてくる。夫婦に子供がいて、生きるためにもがいている。人間として動物として、生き物としての基本がいっぱい詰まった生活。夫婦が互いに相手に対して抱く不満や期待も、とても身近に感じる内容だった。生きることの意味をはじめ、色々なことを考えてしまったけれど、結局のところ、『家族っていいな!』と気付くための映画なのかな、と思った。(彦根 明[建築家])★ 命はどこからくるのか?命を人間に育てるものは何なのか?世界の最底辺の一つ、カルカッタの貧民窟に生まれたビラルという命、それはこの地球上に生まれるあらゆる命が持つエネルギーを体現しているかのようだ。人間の遺伝子には「生きなさい!思いっきり」と書いてあるに違いないとこの映画から思わせられた。全盲の両親ですら自立した仕事をし、命を生み出し、育てることができる。そして当然、世界を愛する事も。鎌仲ひとみ(映画監督『ミツバチの羽音と地球の回転』)
★ 見るものを引きつけてやまないビラルの瞳。目を閉じると彼らの生きている音がにぎやかに聞こえてくる。(佐藤結[映画ライター])
★ インドを旅した人ならスラムに生きる人たちはどう生活しているのか、興味を持ったことはないか。画面を圧倒するのは、混沌とした人間模様か、濃縮された臨場感か。今まで3度見たけど、その度に新しい発見が! インドのかわいい少年が暴れるだけではない映画だ。貧困層の改宗など、インドの今後を考える上でも貴重な一本。(松林要樹[映画監督『相馬看花』『花と兵隊』])
★ この映画には、「インド社会の底辺の貧困を伝えるのだ」といった気負いがない。観ていて疲れない、肩の力を抜いた作品に仕上がっているのは、「この少年を撮りたい」という監督の素朴な動機から生み出されたからだろう。しかしビラルを描こうとすれば、この少年と家族が生きる社会環境も当然映し出される。観客の中にはそこに“インド社会の貧困”“インドでの身体障害者の過酷な現実”を読みとる者も少なくないだろう。だが監督は、「そういう社会的なメッセージをこめて制作したのですか」という観客からの質問に、「この映画にはそんな“社会的なメッセージ”を込めたわけではありません。しかし、観る人がそこにさまざまな社会的なメッセージを読みとるとしたら、それは自由です」と答えた。その姿勢がかえって、押しつけがましさを感じさせずに、でも確実に社会的なメッセージを観客に伝えている。そこがまたいい。(土井敏邦[フリージャーナリスト])
http://www.doi-toshikuni.net/j/column/20091012.html
★ 観ているだけで明日を生きるちからが湧いて来るようなドキュメンタリーである。(青森学[映画ジャッジ!])
★ 全盲の両親も、ビラルも不幸な感じが全くしない。むしろいつも明るくて楽しそうだ。将来の心配はしているけれど、あまり不安がっているようには見えない。見終わって渋谷の人工的な街とそこに歩く人々を目にして、『ビラルの世界』の「明るい貧困」が美しく見えた。(古賀太[日本大学芸術学部 映画学科教授])
★ 『ビラルの世界』は凄い映画だ。これを見て、家族の貧困や、子どもが叩かれたりするシーンに眉をひそめる人がいるかもしれない。だが三歳のビラルの輝く瞳が見ているのはそんなものではない。目の見えない両親が自由に家の中を動き回る姿や、毎日遊ぶ路地で会う仲間たち。それが彼の全世界だ。大人になったら、彼は自分の尻を叩いたその親の手の、なんとも言えぬ温かさを思い出すに違いない。この映画には、世界共通、少なくともアジア世界に共通の、もっともプリミティヴで豊かな人間関係が描かれている。(東陽一[映画監督])
★ 監督やカメラがあの家族の中でまったく邪魔にならず、空気のようなものとして存在していることに驚きました。両親の目が見えないことを知った上で映画を見ていたはずなのですが、ラストシーン近くまでそのことをすっかり忘れて見ていました。観る側もそれほど自然に、スクリーンに映し出される人々や風景を監督と同じく何の先入観もなく愛おしく見ることができました。(49歳男性)
★ ビラルの家は、食に困ることはなく、おそらくインドでは、最貧困層ではない。それでも、私たちの暮らしの快適さとはかけ離れた圧倒的に厳しい生活が、観る者に大きな揺さぶりをかけてくる。それは不思議なことだが、不自由さや重苦しさを伴うL憶というよりは、自分たちと変わらないんだと思う気持ちや、あるいは今の自分に足りない何かを見せられている感覚に、つながっていく。ビラルフ家族の、まさに生きていくことの尊さ、その力強さに、引き込まれた。」(菊川佳代)
+++++++++++++

★ 本物の『スラムドッグ$ミリオネア!』ーガーディアン紙(イギリス)
★ 人生同様、絶望と喜びは隣り合わせだ。ーテヘルカ誌(インド)
★ 山形国際ドキュメンタリー映画祭2009 <アジア千波万波 奨励賞>
アジアの新進監督の新作を集めたプログラムから、国際審査員が選ぶ賞。
[選考コメント]
『ビラルの世界』は、ひとりのムスリムの子ども、盲目の両親、そして近隣コミュニティがおくるコルカタでの生活を、生き生きとそして親密に描く。それは共感と共にある種の居心地悪さを観客にひき起こし、我々を挑発する。力強く確かな映像技術に下支えされ、この作品は暖かい眼差しをもって世界を実に深く見つめている。」(審査員:シャブナム・ヴィルマニ、大木裕之)
★ 山形国際ドキュメンタリー映画祭2009 <コミュニティシネマ賞>
多様な映画の上映を通して、地域社会に豊かな映像文化を根付かせるため、各地での活動を支援するコミュニティシネマセンターによる賞。地域で上映活動を行なう人たちが審査員となり「いちばん観客に見せたい映画」を選ぶ。
[選考理由]
3才のビラルの大きな瞳の輝きに、審査員全員が心を動かされました。この作品のシンプルであり、かつ豊かな世界は、監督の対象を見つめる繊細なまなざしと、それを支える高度な映画的技術によって生み出された烽フです。私たちは、ひとりでも多くの人に“ビラル”に出会ってほしいと思います。」
(審査員:今泉隆子(自主上映団体「チネチッタ」(佐賀)会員)、志尾睦子(高崎映画祭総合ディレクター/シネマテークたかさき支配人)、土肥悦子(シネモンド(金沢)代表)、樋野香織(神戸アートビレッジセンター映画事業担当)、大久保賢一(コミュニティシネマセンター理事/映画評論家)